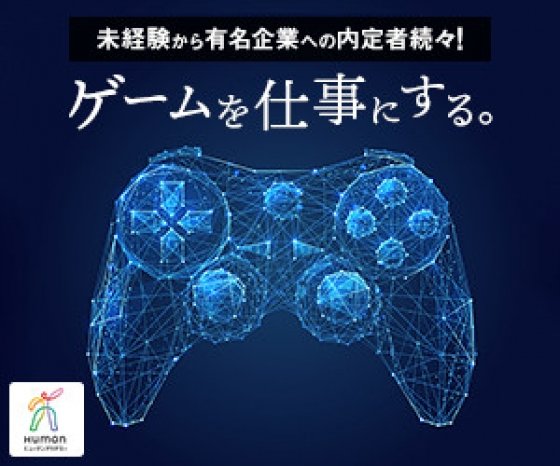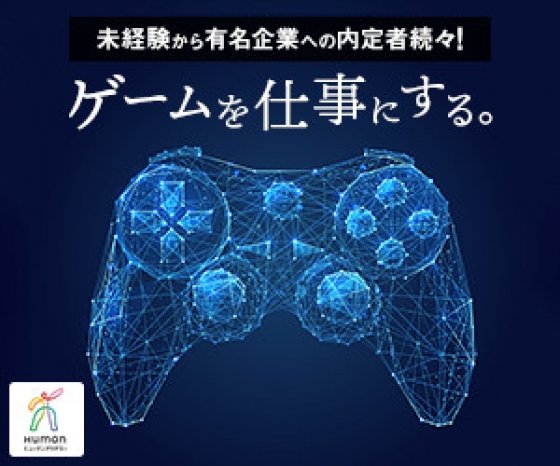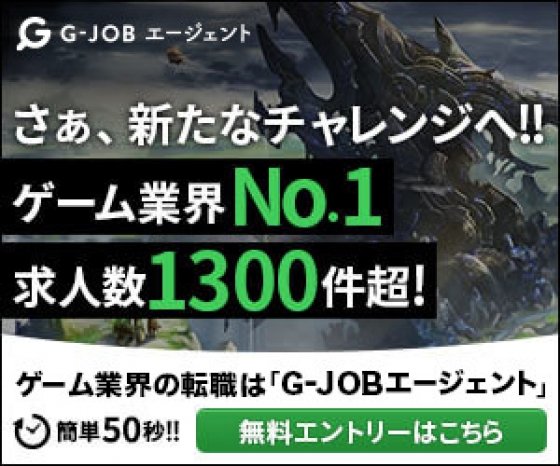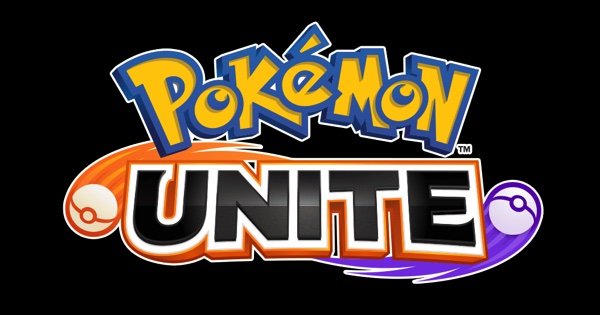【『Steel Hunters』開発者インタビュー&体験レポート】 ウォーゲーミングがPC向けF2Pゲームで成功を重ねてきた理由とは?

- 日本はメカ作品が豊富な国。プラモデル化されたら最高
- リアルさを損なわないためのロボットのサイズ設定
- F2Pタイトルのマネタイズ成功の秘訣とは?
- 1割が既存ユーザー、3割が復帰ユーザー
- 『Steel Hunters』体験レポート:フィジカルだけでは思い通りに勝てない戦略重視のTPS
ミリタリー系オンラインマルチプレイゲームで知られるウォーゲーミングが開発した、まったく新しいPvPvEシューティングゲーム『Steel Hunters』。その開発者によるプレゼンテーションとメディア向け体験会が、3月7日(木)に都内で開催された。

ウォーゲーミングと言えば、リアルな戦車戦を楽しめる『World of Tanks』を筆頭に、戦闘機の『World of Warplanes』や、戦艦バトルの『World of Warships』といった3作品が有名だ。いずれも日本のミリタリーファンの支持も根強く、運営しているゲームの数に比べると、特に日本での知名度と人気は定着している。

それぞれのタイトルを用いてeスポーツの国際大会なども行われてきたが、コアな戦車・戦艦・戦闘機ファンや、コミュニティを大切にしてきた会社、というイメージが強い。実際、『WoT』は2010年のリリース以来今年で15周年を迎え、他のIPとのコラボも相まって今なお熱狂的なプレーヤーが世界中に存在する。
今回は、そんな同社にとって新たな挑戦となるオリジナルメカの新作にどんな期待を寄せているのか、eスポーツ全盛の時代にマルチプレーオンラインゲームで収益を上げるための秘訣も聞いてみた。
──あのウォーゲーミングがロボットを主役にしたゲームを作ると知って、個人的にも非常に楽しみにしていました。もともと日本は『機動戦士ガンダム』から『新世紀エヴァンゲリオン』まで、様々なメカアニメがあり、ゲームでも『アーマード・コアVI』が世界中で人気を博しました。ウォーゲーミングとして日本のゲームファンに対してどんな印象を持ちですか?
ルーク:日本の皆さんには、きっとこの作品を受け入れていただけるだろうという期待があります。というのも、日本ではメカに対して強い関心を持っている方が多く、素晴らしいメカ作品もたくさんあるからです。
私自身も「ガンプラ」などのプラモデル作りが好きで、将来的には『Steel Hunters』のメカたちがプラモデル化されたら最高だなと思っています。
──そのためには、バンダイナムコの作品ともコラボしたいですね(笑)。デモプレイや映像を見た時、『Steel Hunters』のハンター(ゲーム内のロボットの呼称)がとても“人間的”な動きをしていて、『エヴァンゲリオン』を連想しました。設定では人間がロボットに“乗る”のではなく、ロボットそのものがプレイヤーの分身になると。この発想はどこから来たんでしょう?

ルーク:当初は、パイロットがロボットに乗り込むという設定も検討していました。しかしそれだと、ゲームデザインや開発において制約が多くなってしまうんです。何よりも「ロボットを操作しているゲーム」ではなく、「ロボットを操る人間を操作するゲーム」になってしまい、没入感が損なわれる懸念がありました。
そのため、今回は「ロボット=プレーヤー自身」という構図にしています。これにより、画面に映るロボットはプレイヤーそのものという感覚になり、プレー体験の一体感が高まると考えています。
──具体的には、脳波で操作しているようなイメージですか?
ルーク:本作の世界は「Mayday Omega」という大きな災害により、“スターフォール”という地球外からの希少物質が現れ、それが人類の新たなエネルギー源となっています。この「スターフォール」の影響により、人間の“魂”や“記憶”がロボット(ハンター)に宿るのです。ハンターの内部には魂や記憶を格納する器のようなものがあり、そこに人間性が残されているという設定で、新たな生命体になるというイメージです。
──個人的には、そういった世界観やキャラクターのバックストーリーを読むのが好きなのですが、『Steel Hunters』ではどれくらい詳細に作り込む予定なのでしょうか?
ルーク:公式YouTubeチャンネルでは、世界観やハンターの背景などを紹介するコンテンツを順次投稿しています。
例えば「最初のハンターがどう生まれたか」「かつて人間だったときの生活」など、プレイヤーがストーリーに深く入り込めるような内容になっています。これは今後も随時追加されていく予定です。
──デモプレイの中で、「ロボットが実在の建物の中を歩いたり破壊できるところにも注目してほしい」とおっしゃっていましたが、どれくらいのサイズなのでしょうか?
ルーク:ヒューマノイド型のハンターは約8mほどの高さがあり、四足歩行など動物モチーフのものはやや小型ですが、それでも数mのサイズ感になっています。
──対戦ゲームとしてのハンターごとの強さの違いは?
ルーク:ハンターの種類によって利点も弱点も異なります。タンク系のように正面が硬いタイプでは、頭部ではなく他の部位が弱点になる場合もあります。この辺はゲーム性を重視し、世界観に縛られすぎないようにしているため、弱点の設定は柔軟にしていますね。

──実際にプレイしてみて、“戦車のような重厚さ”があり、ロボットを動かしているというリアル感と手応えを感じました。
ルーク:ありがとうございます。そこはこだわりの一つです。ハンターに転生するという設定では、元の肉体はすでに使えない状態。だからこそ、人間っぽい動きの中にも、例えば歩く際にモーターが駆動してから足を踏み出すとか、ダッシュの前の溜めの動作など、重みのある動きや演出を大事にしています。

──『Steel Hunters』はこれまでの『World of Tanks』シリーズのようにリアルに存在する製品とは真逆で、まったく新しいデザインと世界観ですが、社内に「こういうゲームを作りたい!」と提案した方がいたんですか?
ルーク:はい。従来のリアル路線とは異なることをやってみたいという想いがありました。ただ、戦略性やスローペースでの駆け引きといったウォーゲーミングらしさはしっかり残しています。
──そこは強く感じました。見た目は最近のハイスピードなシューターという印象でしたが、ハンターを少し動かしただけで「あ、これは確かにウォーゲーミングのゲームだ」と。
ルーク:そう言っていただけるのは嬉しいですね。自由度が高い分、しっかり制限も設けることで、ウォーゲーミングらしさを損なわないように心がけています。

──私どもはeスポーツ専門メディアですが、F2P(フリートゥープレイ)のゲームで、御社ほど成長・継続しているケースはあまり見たことがありません。今回のプロジェクトにおいてはどんなふうにマネタイズ化を進める予定なのでしょうか?
ローラン:私たちは4月2日から始まる最初の「シーズン0」=アーリーアクセス版では、マネタイズを一切行わないと決めています。ただし、正式サービスが始まる「シーズン1」からは、バトルパス形式で少額課金を導入する予定です。
大切にしているのは“公平性”です。これが成功の鍵だと考えています。そのため、マネタイズ要素はゲーム性に影響を与えないスキンやバナー、見た目のカスタマイズなどに限定する方針です。価格も抑えめにし、幅広いプレイヤーが楽しめるような低価格帯の商品展開を目指しています。
また、アーリーアクセスを通じてプレイヤーの需要をしっかり把握し、それに基づいて提供内容を調整していきたいと考えています。ただし、それほど長期間行うことは考えていません。
──お話を聞くと簡単そうですが、課金しないと使えないキャラクターがいるなど、F2Pタイトルのマネタイズにもいろいろな方法があります。ウォーゲーミングが成功している理由は?
ローラン:ひとつは“自信”です。私たちは15年にわたりさまざまなタイトルを長期運営してきました。その中で成功と失敗から多くを学び、プレイヤーのニーズを正しく捉え、最適なポイントにリソースを集中させる技術が磨かれてきたのだと思います。
この会議室を見ていただければわかる通り(※体験会はウォーゲーミング・ジャパンのオフィスにて行われた)、私たちはコンセプトや情熱をとても大切にしており、それをプレイヤーにしっかり届ける努力をしています。“プレイヤーファースト”の精神が根付いていることも、成功の要因だと思います。

──収益について、一般的にF2Pビジネスでは高額課金するマニア層、少し課金するライト層、まったく課金しない無課金層といったユーザーがいますが、どういったユーザーが多いのでしょうか?
ローラン:タイトルによっても異なるので一概には言えませんが、弊社のゲームはニッチなジャンルが多く、情熱的なコアファンが多いのが特徴です。その中には喜んで課金してくださる方も少なくなく、そういった方々の支えがあって会社としての運営や新作開発が可能になっています。正確な割合は把握していませんが、確実に“熱量の高いファン”を獲得できている実感はありますね。
ウォーゲーミングのファンは非常に愛着心が強く、「ウォーゲーミングだからこそ楽しめる」と感じてくださる方が多いんです。そうした方々のおかげで、私たちもゲーム提供を継続できています。
──ファンの熱量こそが財産になっているということですね。ただ、『Steel Hunters』は新規のロボットゲームですし、従来のウォーゲーミングファンとはターゲットは変わりそうですね。
ローラン:はい。今回のタイトルは明確に“新しい層”をターゲットにしています。従来の『World of Tanks』や『World of Warships』は年齢層が比較的高めでしたが、今回のタイトルではより若い層にも響くようなデザインやアプローチを採用しています。

とはいえ、既存ファンを排除しているわけではありません。実際にテスト段階では、参加者の約10%が既存タイトルのユーザーです。また、約30%はかつてウォーゲーミングのゲームをプレイしていたけれど離脱した人たちが、この新作をきっかけに戻ってきてくれたというデータもあります。
──既存ユーザーが10%というのは多いですか? 少ないですか?
ローラン:数として多い少ないは一概に言えませんが、私たちとしては嬉しい結果です。離れてしまった方が戻ってきてくれるのも嬉しいですし、残りの約6割の新しい層にもリーチできているという実感があるので、幅広い層へのアプローチがうまくいっているのかなと思います。
最後に少しだけ、体験レポートの印象もお伝えしよう。
『Steel Hunters』では2人1組のタッグを組み、最大6チーム12人でひとつのマップ内で戦う。勝利条件は(1)すべてのライバルを倒す、(2)「脱出ゾーン(エクストラクションポイント)」を最後まで守り抜くことだ。
序盤は、マップ内に点在するNPCのドローンなどを破壊することでアイテムや経験値を獲得し、ある程度装備が固まった段階で戦うというのがセオリー。メイン武器やスキルはハンター固有のものがあるため、武器などが拾えなくても戦うことはできる。こういった部分はMOBAに近く、これまでのバトルロイヤルなどにはあまりなかった要素となっている。
また、アイテムの中には敵の「タグ」など、ライバルを倒すメリットも用意されている。生き残りを目指すよりも、積極的に敵を倒していくゲーム性になっていることは間違いない。

ハンターの操作は、一般的なシューターと同様にWASDによる移動とマウスによるエイム・射撃がメイン。「shift」で走ったり「ctrl」で避け・移動なども行える。移動がゆっくりなこともあってか、シールド(体力)は総じて暑く、『オーバーウォッチ2』のように数発で倒されるということはない。
筆者が感じた面白さは、『World of シリーズ』のように着弾点を予測して撃つ射撃はもちろん、これまでの同社の作品にはなかった近距離攻撃が挙げられる。自分の移動が遅いということは相手の移動も同様なわけだが、いかにしてダメージを与えるか、近づいて攻撃するかなど、頭を使って戦略を立てるところは友人などとタッグを組むと面白そうだ。

その裏返しとして、昨今のシューターをプレーしてきた方からすると、楽しいと感じるかは評価が分かれるところかもしれない。個人的には、ウォーゲーミングらしさを感じつつも、純粋にカッコいいと思えるメカデザインなども手伝って、『Steel Hunters』という新しいジャンルにチャレンジしてみたいと思えた。
4月2日からはアーリーアクセスが始まり、初期7体のハンターがすぐに使えるようになる。タンク、スナイパー、偵察、回復など、どれも個性あふれるキャラばかりだ。ルーク氏によれば「やはり珍しいのか、動物系のハンターが人気」とのことだった。
目の肥えた日本のユーザーからどんな評価を受けるのか、そして新たなeスポーツ展開が期待できるのか。『Steel Hunters』の今後の展開にも期待したい。
Steel Hunters:https://steelhunters.com/ja
Steel Hunters Steamページ:https://store.steampowered.com/app/1691340/STEEL_HUNTERS/?l=japanese
© 2019 - 2025 Steel Hunters. All rights reserved.

今回発表された『Steel Hunters』は巨大なメカ同士が戦う基本料金無料のPvPvEシューター。日本で大ヒットした『アーマード・コア』的な雰囲気に見えるが、中身は全く違う新しい世界観だ
ウォーゲーミングと言えば、リアルな戦車戦を楽しめる『World of Tanks』を筆頭に、戦闘機の『World of Warplanes』や、戦艦バトルの『World of Warships』といった3作品が有名だ。いずれも日本のミリタリーファンの支持も根強く、運営しているゲームの数に比べると、特に日本での知名度と人気は定着している。

ウォーゲーミングの代表作である『World of Tanks』は、多人数対戦ゲームとして長い人気を誇る
それぞれのタイトルを用いてeスポーツの国際大会なども行われてきたが、コアな戦車・戦艦・戦闘機ファンや、コミュニティを大切にしてきた会社、というイメージが強い。実際、『WoT』は2010年のリリース以来今年で15周年を迎え、他のIPとのコラボも相まって今なお熱狂的なプレーヤーが世界中に存在する。
今回は、そんな同社にとって新たな挑戦となるオリジナルメカの新作にどんな期待を寄せているのか、eスポーツ全盛の時代にマルチプレーオンラインゲームで収益を上げるための秘訣も聞いてみた。
ローラン・ラルティジアン氏(写真左)
マーケティングディレクター。ゲームメディア、eコマース、ゲームパブリッシング分野で11年以上の経験を持つマーケティングのエキスパート。
ルーク・ニコルズ氏(写真右)
ヘッドオブプレイヤーインタラクションズ。ウォーゲーミングにて11年以上にわたってコミュニティやプレイヤーとのコミュニケーション領域の専門家。『Steel Hunters』におけるプレイヤーインタラクション全般(コミュニティ運営、カスタマーサポート、コンテンツ、CRMなど)を統括する。
マーケティングディレクター。ゲームメディア、eコマース、ゲームパブリッシング分野で11年以上の経験を持つマーケティングのエキスパート。
ルーク・ニコルズ氏(写真右)
ヘッドオブプレイヤーインタラクションズ。ウォーゲーミングにて11年以上にわたってコミュニティやプレイヤーとのコミュニケーション領域の専門家。『Steel Hunters』におけるプレイヤーインタラクション全般(コミュニティ運営、カスタマーサポート、コンテンツ、CRMなど)を統括する。
日本はメカ作品が豊富な国。プラモデル化されたら最高
──あのウォーゲーミングがロボットを主役にしたゲームを作ると知って、個人的にも非常に楽しみにしていました。もともと日本は『機動戦士ガンダム』から『新世紀エヴァンゲリオン』まで、様々なメカアニメがあり、ゲームでも『アーマード・コアVI』が世界中で人気を博しました。ウォーゲーミングとして日本のゲームファンに対してどんな印象を持ちですか?
ルーク:日本の皆さんには、きっとこの作品を受け入れていただけるだろうという期待があります。というのも、日本ではメカに対して強い関心を持っている方が多く、素晴らしいメカ作品もたくさんあるからです。
私自身も「ガンプラ」などのプラモデル作りが好きで、将来的には『Steel Hunters』のメカたちがプラモデル化されたら最高だなと思っています。
──そのためには、バンダイナムコの作品ともコラボしたいですね(笑)。デモプレイや映像を見た時、『Steel Hunters』のハンター(ゲーム内のロボットの呼称)がとても“人間的”な動きをしていて、『エヴァンゲリオン』を連想しました。設定では人間がロボットに“乗る”のではなく、ロボットそのものがプレイヤーの分身になると。この発想はどこから来たんでしょう?

ハンターの立ち方や動きなどからは、物理的なロボットの強度などよりも人間らしいしなやかさとポーズのカッコ良さを感じる
ルーク:当初は、パイロットがロボットに乗り込むという設定も検討していました。しかしそれだと、ゲームデザインや開発において制約が多くなってしまうんです。何よりも「ロボットを操作しているゲーム」ではなく、「ロボットを操る人間を操作するゲーム」になってしまい、没入感が損なわれる懸念がありました。
そのため、今回は「ロボット=プレーヤー自身」という構図にしています。これにより、画面に映るロボットはプレイヤーそのものという感覚になり、プレー体験の一体感が高まると考えています。
──具体的には、脳波で操作しているようなイメージですか?
ルーク:本作の世界は「Mayday Omega」という大きな災害により、“スターフォール”という地球外からの希少物質が現れ、それが人類の新たなエネルギー源となっています。この「スターフォール」の影響により、人間の“魂”や“記憶”がロボット(ハンター)に宿るのです。ハンターの内部には魂や記憶を格納する器のようなものがあり、そこに人間性が残されているという設定で、新たな生命体になるというイメージです。
──個人的には、そういった世界観やキャラクターのバックストーリーを読むのが好きなのですが、『Steel Hunters』ではどれくらい詳細に作り込む予定なのでしょうか?
ルーク:公式YouTubeチャンネルでは、世界観やハンターの背景などを紹介するコンテンツを順次投稿しています。
例えば「最初のハンターがどう生まれたか」「かつて人間だったときの生活」など、プレイヤーがストーリーに深く入り込めるような内容になっています。これは今後も随時追加されていく予定です。
最初のハンターである「RAZORSIDE」の誕生秘話。戦場の英雄の意識が科学者の手によってハンターに移される
3月31日に公開されたばかりのタンク系ハンター「URSUS(アーサス」のストーリー。スターフォールをめぐる悲しくも切ない物語が展開される
リアルさを損なわないためのロボットのサイズ設定
──デモプレイの中で、「ロボットが実在の建物の中を歩いたり破壊できるところにも注目してほしい」とおっしゃっていましたが、どれくらいのサイズなのでしょうか?
ルーク:ヒューマノイド型のハンターは約8mほどの高さがあり、四足歩行など動物モチーフのものはやや小型ですが、それでも数mのサイズ感になっています。
──対戦ゲームとしてのハンターごとの強さの違いは?
ルーク:ハンターの種類によって利点も弱点も異なります。タンク系のように正面が硬いタイプでは、頭部ではなく他の部位が弱点になる場合もあります。この辺はゲーム性を重視し、世界観に縛られすぎないようにしているため、弱点の設定は柔軟にしていますね。

ハンターにはヒューマノイドタイプと動物タイプなどがあり、機動性、装甲の強さなどは特性に応じて異なる
──実際にプレイしてみて、“戦車のような重厚さ”があり、ロボットを動かしているというリアル感と手応えを感じました。
ルーク:ありがとうございます。そこはこだわりの一つです。ハンターに転生するという設定では、元の肉体はすでに使えない状態。だからこそ、人間っぽい動きの中にも、例えば歩く際にモーターが駆動してから足を踏み出すとか、ダッシュの前の溜めの動作など、重みのある動きや演出を大事にしています。

ハンターのひとつ、HEATBREAKERのデザイン。丸みを帯びた人間に近いデザインの細部にメカ好きとしてのこだわりが垣間見える
──『Steel Hunters』はこれまでの『World of Tanks』シリーズのようにリアルに存在する製品とは真逆で、まったく新しいデザインと世界観ですが、社内に「こういうゲームを作りたい!」と提案した方がいたんですか?
ルーク:はい。従来のリアル路線とは異なることをやってみたいという想いがありました。ただ、戦略性やスローペースでの駆け引きといったウォーゲーミングらしさはしっかり残しています。
──そこは強く感じました。見た目は最近のハイスピードなシューターという印象でしたが、ハンターを少し動かしただけで「あ、これは確かにウォーゲーミングのゲームだ」と。
ルーク:そう言っていただけるのは嬉しいですね。自由度が高い分、しっかり制限も設けることで、ウォーゲーミングらしさを損なわないように心がけています。

ハンターを選択する「格納庫」の画面。メカデザインや武器など、詳細なこだわりが見られる。ぜひフィギュア化もしてほしい!
F2Pタイトルのマネタイズ成功の秘訣とは?
──私どもはeスポーツ専門メディアですが、F2P(フリートゥープレイ)のゲームで、御社ほど成長・継続しているケースはあまり見たことがありません。今回のプロジェクトにおいてはどんなふうにマネタイズ化を進める予定なのでしょうか?
ローラン:私たちは4月2日から始まる最初の「シーズン0」=アーリーアクセス版では、マネタイズを一切行わないと決めています。ただし、正式サービスが始まる「シーズン1」からは、バトルパス形式で少額課金を導入する予定です。
大切にしているのは“公平性”です。これが成功の鍵だと考えています。そのため、マネタイズ要素はゲーム性に影響を与えないスキンやバナー、見た目のカスタマイズなどに限定する方針です。価格も抑えめにし、幅広いプレイヤーが楽しめるような低価格帯の商品展開を目指しています。
また、アーリーアクセスを通じてプレイヤーの需要をしっかり把握し、それに基づいて提供内容を調整していきたいと考えています。ただし、それほど長期間行うことは考えていません。
──お話を聞くと簡単そうですが、課金しないと使えないキャラクターがいるなど、F2Pタイトルのマネタイズにもいろいろな方法があります。ウォーゲーミングが成功している理由は?
ローラン:ひとつは“自信”です。私たちは15年にわたりさまざまなタイトルを長期運営してきました。その中で成功と失敗から多くを学び、プレイヤーのニーズを正しく捉え、最適なポイントにリソースを集中させる技術が磨かれてきたのだと思います。
この会議室を見ていただければわかる通り(※体験会はウォーゲーミング・ジャパンのオフィスにて行われた)、私たちはコンセプトや情熱をとても大切にしており、それをプレイヤーにしっかり届ける努力をしています。“プレイヤーファースト”の精神が根付いていることも、成功の要因だと思います。

体験会で振る舞われたケータリングも遊び心たっぷり
1割が既存ユーザー、3割が復帰ユーザー
──収益について、一般的にF2Pビジネスでは高額課金するマニア層、少し課金するライト層、まったく課金しない無課金層といったユーザーがいますが、どういったユーザーが多いのでしょうか?
ローラン:タイトルによっても異なるので一概には言えませんが、弊社のゲームはニッチなジャンルが多く、情熱的なコアファンが多いのが特徴です。その中には喜んで課金してくださる方も少なくなく、そういった方々の支えがあって会社としての運営や新作開発が可能になっています。正確な割合は把握していませんが、確実に“熱量の高いファン”を獲得できている実感はありますね。
ウォーゲーミングのファンは非常に愛着心が強く、「ウォーゲーミングだからこそ楽しめる」と感じてくださる方が多いんです。そうした方々のおかげで、私たちもゲーム提供を継続できています。
──ファンの熱量こそが財産になっているということですね。ただ、『Steel Hunters』は新規のロボットゲームですし、従来のウォーゲーミングファンとはターゲットは変わりそうですね。
ローラン:はい。今回のタイトルは明確に“新しい層”をターゲットにしています。従来の『World of Tanks』や『World of Warships』は年齢層が比較的高めでしたが、今回のタイトルではより若い層にも響くようなデザインやアプローチを採用しています。

リアルミリタリーゲームにはなかった特殊効果やスキルなど、自由な発想は若者にも受け入れられるか
とはいえ、既存ファンを排除しているわけではありません。実際にテスト段階では、参加者の約10%が既存タイトルのユーザーです。また、約30%はかつてウォーゲーミングのゲームをプレイしていたけれど離脱した人たちが、この新作をきっかけに戻ってきてくれたというデータもあります。
──既存ユーザーが10%というのは多いですか? 少ないですか?
ローラン:数として多い少ないは一概に言えませんが、私たちとしては嬉しい結果です。離れてしまった方が戻ってきてくれるのも嬉しいですし、残りの約6割の新しい層にもリーチできているという実感があるので、幅広い層へのアプローチがうまくいっているのかなと思います。
『Steel Hunters』体験レポート:フィジカルだけでは思い通りに勝てない戦略重視のTPS
最後に少しだけ、体験レポートの印象もお伝えしよう。
『Steel Hunters』では2人1組のタッグを組み、最大6チーム12人でひとつのマップ内で戦う。勝利条件は(1)すべてのライバルを倒す、(2)「脱出ゾーン(エクストラクションポイント)」を最後まで守り抜くことだ。
序盤は、マップ内に点在するNPCのドローンなどを破壊することでアイテムや経験値を獲得し、ある程度装備が固まった段階で戦うというのがセオリー。メイン武器やスキルはハンター固有のものがあるため、武器などが拾えなくても戦うことはできる。こういった部分はMOBAに近く、これまでのバトルロイヤルなどにはあまりなかった要素となっている。
また、アイテムの中には敵の「タグ」など、ライバルを倒すメリットも用意されている。生き残りを目指すよりも、積極的に敵を倒していくゲーム性になっていることは間違いない。

対戦中の画面右には、いまゲットできるクエストなどが表示されるため、次に何をすればいいかの短期的な目標がわかりやすい
ハンターの操作は、一般的なシューターと同様にWASDによる移動とマウスによるエイム・射撃がメイン。「shift」で走ったり「ctrl」で避け・移動なども行える。移動がゆっくりなこともあってか、シールド(体力)は総じて暑く、『オーバーウォッチ2』のように数発で倒されるということはない。
筆者が感じた面白さは、『World of シリーズ』のように着弾点を予測して撃つ射撃はもちろん、これまでの同社の作品にはなかった近距離攻撃が挙げられる。自分の移動が遅いということは相手の移動も同様なわけだが、いかにしてダメージを与えるか、近づいて攻撃するかなど、頭を使って戦略を立てるところは友人などとタッグを組むと面白そうだ。

体験会はAI戦だったが、多人数のプレーヤー同士の対戦がどうなるかも楽しみなポイント
その裏返しとして、昨今のシューターをプレーしてきた方からすると、楽しいと感じるかは評価が分かれるところかもしれない。個人的には、ウォーゲーミングらしさを感じつつも、純粋にカッコいいと思えるメカデザインなども手伝って、『Steel Hunters』という新しいジャンルにチャレンジしてみたいと思えた。
4月2日からはアーリーアクセスが始まり、初期7体のハンターがすぐに使えるようになる。タンク、スナイパー、偵察、回復など、どれも個性あふれるキャラばかりだ。ルーク氏によれば「やはり珍しいのか、動物系のハンターが人気」とのことだった。
目の肥えた日本のユーザーからどんな評価を受けるのか、そして新たなeスポーツ展開が期待できるのか。『Steel Hunters』の今後の展開にも期待したい。
Steel Hunters:https://steelhunters.com/ja
Steel Hunters Steamページ:https://store.steampowered.com/app/1691340/STEEL_HUNTERS/?l=japanese
© 2019 - 2025 Steel Hunters. All rights reserved.
 eSports World の
eSports World の Discord をフォローしよう
 SALE
SALE
 大会
大会
 チーム
チーム
 他にも...?
他にも
他にも...?
他にも